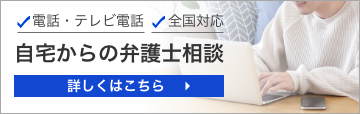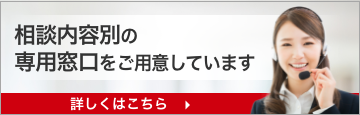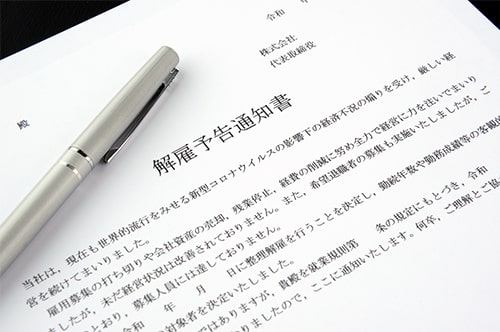育休中における有給の取り扱い方は? 注意点を弁護士が解説
- 労働問題
- 有給
- 育休中

2022年度に埼玉県内の総合労働相談コーナーに寄せられた相談は5万2753件でした。
労働問題のひとつとして、育休にかかわるものがあります。たとえば、育休中の労働者は出勤しませんが「有給休暇は一切付与されないのか?」といった疑問があります。
労働基準法上、有給休暇との関係では、育休期間は出勤したものとみなされます。したがって、育休中の労働者が復職したら、勤続年数などに応じた有給休暇を付与する必要がある点にご注意ください。
本記事では、有給休暇に関する育休期間の取り扱いなどをベリーベスト法律事務所 越谷オフィスの弁護士が解説します。
出典:「『令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況(埼玉労働局)』を公表します」(埼玉労働局)
1、有給休暇に関する育休期間の取り扱い
年次有給休暇は、出勤率が一定以上の労働者に対して付与する必要があります。
育児休業期間については、出勤したものとみなして有給休暇の日数を計算する点にご注意ください。
-
(1)育休(育児休業)とは
「育児休業」とは、子どもが一定の年齢に達するまで、その養育のために労働者が利用できる休業制度です。育児・介護休業法に基づき、育児休業の取得は労働者の権利として認められています。
すべての無期雇用労働者と、子が1歳6か月に達するまでに労働契約の期間が満了することが明らかでない有期雇用労働者は、育児休業を取得できます(育児・介護休業法第5条第1項)。
育児休業の期間は、原則として子が1歳に達するまでです(育児・介護休業法第9条第2項2号)。ただし、子どもが保育所に入れない場合などには、最長で子が2歳に達するまで育児休業を延長できることがあります。 -
(2)有給休暇とは
「有給休暇」とは、労働基準法に基づき、労働者に対して付与される有給の休暇です。
「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき、労働者が仕事を休んだ日は原則として無給となります。しかし、有給休暇については例外的に、所定労働時間働いた場合と同等の賃金が支払われます。
後述のとおり、有給休暇が付与されるか否かは出勤率によって決まります。そのため有給休暇との関係で、育休期間を出勤・欠勤のどちらと取り扱うのかが問題となります。 -
(3)有給休暇との関係では、育休中は出勤したものとみなされる
有給休暇との関係では、育児休業を取得した期間は出勤したものとみなされます(労働基準法第39条第10項)。
したがって、育休期間と実際に出勤した期間を合算した結果、出勤率が有給休暇の取得要件(後述)を満たしていれば、労働者に対して有給休暇を付与しなければなりません。 -
(4)有給休暇との関係で、出勤したものとみなされるその他の休業
育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業以外にも、以下の休業期間については、有給休暇との関係で出勤したものとみなされます(労働基準法第39条第10条)。
- 業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
- 育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業をした期間
- 労働基準法第65条に規定する産前産後休業をした期間
また、有給休暇を取得した日についても、次に付与される有給休暇との関係で出勤したものとみなされます。
2、有給休暇が付与される条件・日数
有給休暇は、出勤率が一定以上の労働者に対して、継続勤務期間などに応じた日数が付与されます。
フルタイム労働者(正社員)のみならず、パートタイム労働者(パート・アルバイトなど)にも有給休暇が付与されることがあります。
-
(1)有給休暇が付与される条件
有給休暇が付与されるのは、以下の基準期間において、継続勤務をして全労働日の8割以上出勤した労働者です(労働基準法第39条第1項、第2項)。
【基準期間】- ① 雇入れ後、最初に付与される有給休暇:雇入れから6か月間
- ② 2回目以降に付与される有給休暇:付与日の前1年間
前述のとおり、育休中の期間は出勤したものとみなして出勤率を算出します。
(例)- 基準期間の1年間につき、すべて育児休業を取得した場合:出勤率は100%なので、有給休暇が付与される
- 基準期間の1年間のうち、半年間につき育児休業を取得し、残りの半年間の出勤率が70%だった場合:出勤率は85%なので、有給休暇が付与される
-
(2)付与される有給休暇の日数
労働者に対して付与される有給休暇の付与日数は、フルタイム労働者(※)とそうでない労働者で異なります。
(※フルタイム労働者:以下のいずれかに該当する労働者)
- 1週間の所定労働日数が5日以上
- 1年間の所定労働日数が217日以上
- 1週間の所定労働時間が30時間以上
フルタイム労働者に対しては、継続勤務期間に応じて、以下の日数の有給休暇が付与されます(労働基準法第39条第1項、第2項、労働基準法施行規則24条の3第3項)。
継続勤務期間 付与される有給休暇の日数 6か月 10日 1年6か月 11日 2年6か月 12日 3年6か月 14日 4年6か月 16日 5年6か月 18日 6年6か月以上 20日
(例)- フルタイム労働者が、雇入れの1年6か月後から1年間育児休業を取得した場合:育児休業明け(=雇入れの2年6か月後)に12日間の有給休暇が付与される
これに対して、フルタイム労働者以外の労働者に対しては、継続勤務期間と所定労働日数に応じて、以下の日数の有給休暇が付与されます(労働基準法第39条第3項)。
※1週間の所定労働日数と1年間の所定労働日数のうち、有給休暇の日数が多くなる方が適用されます。1週間の所定労働日数 4日 3日 2日 1日 1年間の所定労働日数 169日以上216日以下 121日以上168日以下 73日以上120日以下 48日以上72日以下 継続勤務期間 6か月 7日 5日 3日 1日 1年6か月 8日 6日 4日 2日 2年6か月 9日 6日 4日 2日 3年6か月 10日 8日 5日 2日 4年6か月 12日 9日 6日 3日 5年6か月 13日 10日 6日 3日 6年6か月以上 15日 11日 7日 3日
(例)- 1週間の所定労働日数が4日、1年間の所定労働日数が215日の労働者が、雇入れの1年6か月後から1年間育児休業を取得した場合:育児休業明け(=雇入れの2年6か月後)に9日間の有給休暇が付与される
3、育休明けの従業員に対して、年5日の有給休暇を取得させる義務はあるのか?
有給休暇が10日以上付与される労働者に対しては、そのうち5日間につき時季を定めて付与しなければなりません(労働基準法第39条第7項)。
育休明けの労働者に対しても、年5日の有給休暇を取得させる義務が生じることがあるので注意が必要です。。
-
(1)年5日の有給休暇を取得させる義務とは
有給休暇が10日以上付与される労働者に対しては、そのうち5日間につき、使用者において時季を定めて与える必要があります(労働基準法第39条第7項)。
上司や同僚に遠慮して有給休暇の取得が進まない労働者が多い状況に鑑み、確実に一定日数の有給休暇を取得させるため、2019年4月から新たに導入された制度です。
なお、労働者の請求に応じて付与した有給休暇の日数、および計画的に付与した有給休暇の日数については、時季を定めて与える義務が免除されます(同条第8項)。 -
(2)育休明けの従業員に年5日の有給休暇を取得させるべきケース
有給休暇の付与を受けた後に育児休業へ入った労働者についても、付与された有給休暇の日数が10日以上である場合は、年5日の有給休暇を取得させる会社の義務が生じることがあります。
年5日の有給休暇を取得させる義務が生じるかどうかは、育児休業から復職する時期によって異なります。
復職後、次の基準期間が始まるまでに出勤日が5日以上ある場合は、残りの出勤日の中から5日間を指定して有給休暇を取得させなければなりません。
これに対して、次の基準期間が始まるまでの出勤日が5日未満の場合は、その残り日数について有給休暇を取得させれば足ります。ただし、次回に付与される有給休暇については、改めて年5日の有給休暇を取得させる義務が生じる点にご注意ください。
4、人事労務に関するご相談は弁護士へ
企業における労務管理は、労働基準法その他の法令を順守して行う必要があります。不適切な労務管理を行っていると、労働者との間でトラブルに発展するおそれがあるので注意が必要です。
企業が労務管理を行うに当たっては、弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。弁護士に相談すれば、労働基準法等の法令に基づく正しい労務管理の方法につき、具体的なアドバイスを受けることができます。
また、万が一労働者との間でトラブルに発展した際にも、協議や法的手続きなどの対応を弁護士に一任できます。
人事・労務管理の方法やトラブル対応などについてお悩みの企業は、弁護士にご相談ください。
お問い合わせください。
5、まとめ
労働者に対して有給休暇を付与すべきか否かは、労働者の出勤率によって決まります。
育休中の期間は出勤したものとみなされる点を考慮して、有給休暇の付与の要否を適切に判断しましょう。
有給休暇の付与に当たっては、労働基準法のルールを正しく適用する必要があります。そのためには、弁護士のアドバイスを受けるのが安心です。
ベリーベスト法律事務所
越谷オフィスでは、人事・労務管理に関する企業のご相談を随時受け付けております。有給休暇の取り扱いに加えて、賃金や労働時間の取り扱いや社内規定の整備などについても、クライアント企業の実態に合わせてアドバイスいたします。
人事・労務管理に関する企業のお悩みは、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています