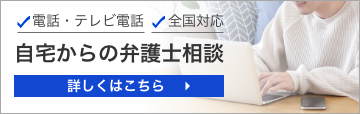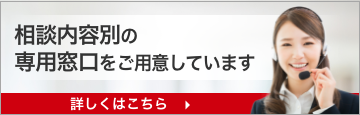従業員を解雇する場合の会社側のデメリットとは? 注意点も解説
- 一般企業法務
- 解雇
- 会社
- デメリット
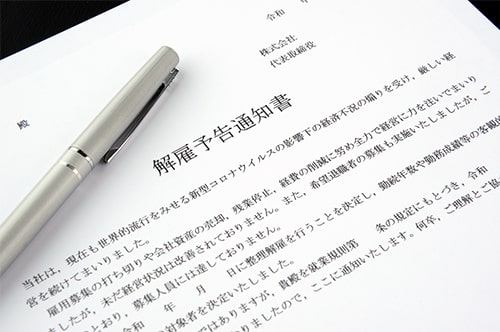
2022年度に埼玉県内の総合労働相談コーナーに寄せられた民事上の個別労働紛争相談は9590件で、そのうち解雇に関するものは1280件でした。
能力が不足している従業員や、トラブルを起こしがちな従業員がいる場合、会社としては解雇したいところかもしれません。
しかし、従業員を解雇することには、会社にとってのデメリットが多数存在します。弁護士のアドバイスを受けて、解雇のリスクを正しく理解した上で、本当に従業員を解雇すべきかどうか適切に判断しましょう。
本記事では、従業員を解雇することによって生じる会社のデメリットや、不当解雇を避けるためのポイントなどを、ベリーベスト法律事務所 越谷オフィスの弁護士が解説します。
出典:「「令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況(埼玉労働局)」を公表します」(埼玉労働局)
1、解雇とは
「解雇」とは、使用者の一方的意思表によって雇用契約を解除(終了)することをいいます。使用者による「解雇」の意思表示によって従業員が労働者の地位を喪失します。
-
(1)普通解雇・整理解雇・懲戒解雇
解雇には、「普通解雇」「整理解雇」の2種類があります。そして、解雇と同様に労働者の地位を喪失させる処分として、懲戒処分の一種として「懲戒解雇」があります。
- ① 普通解雇:労働能力欠如や規律違反行為などを理由とする整理解雇を除く解雇です。
- ② 整理解雇:会社の経営不振などの経営上の必要性から、人員削減するために行われる解雇です。
- ③ 懲戒解雇:従業員の就業規則違反などの企業秩序違反行為に対する不利益措置としての解雇です。
-
(2)解雇に当たって満たすべき要件
各種類の解雇を行う際には、それぞれ以下の要件を満たす必要があります。
- ① 普通解雇
以下の要件をいずれも満たす必要があります。
・ 普通解雇を行う客観的に合理的な理由があり、かつ普通解雇が社会通念上相当であること
- ② 整理解雇
以下の4要件を総合的に考慮して、整理解雇の有効性が判断されます。
・ 人員削減の必要性:高度の経営危機に陥っており、人員削減の必要性が高いこと
・ 被解雇者選定の合理性:合理的な基準を策定した上で、その基準を合理的に運用して整理解雇の対象者を選定したこと
・ 解雇回避努力義務の履行:役員報酬の削減、希望退職者の募集、新規採用の抑制などの代替手段を尽くしても、なお整理解雇の必要性が高いと認められること
・ 解雇手続の妥当性:対象者や労働組合に対して、整理解雇の必要性などを十分に説明し、納得を得るよう努めたこと
- ③ 懲戒解雇
以下の要件をいずれも満たす必要があります。
・ 就業規則において、懲戒解雇を行うことがある旨が定められていること
・ 労働者の行為が、就業規則等の規定上の懲戒事由に該当すること(懲戒処分を行う客観的合理的理由があること)
・ 労働者の行為の性質および態様その他の事情に照らして、懲戒解雇が社会通念上相当であること
- ① 普通解雇
2、解雇による会社側のデメリット
従業員を解雇することには、会社にとって以下のようなデメリットがあります。これらのデメリットを正しく理解した上で、従業員を解雇してもよいかどうか適切に判断しましょう。
-
(1)解雇予告手当の支払いを要する場合がある
従業員を解雇(懲戒解雇を除く)する際には、原則として30日以上前に、従業員に対して解雇の旨を予告しなければなりません。
解雇予告をしない場合や、解雇予告から30日未満で解雇する場合には、解雇予告手当の支払いが必要となる点に注意が必要です(労働基準法第20条第1項)。 -
(2)不当解雇を主張されてトラブルになるおそれがある
従業員を解雇する際には、前述のとおり、懲戒解雇・整理解雇・普通解雇に対応する要件を満たさなければなりません。
特に、解雇に客観的・合理的理由および社会的相当性を要求する「解雇権濫用の法理」(労働契約法第16条)は、非常に厳格に運用されています。
そのため、従業員に不当解雇を主張され、解雇が無効になってしまう例が少なくありません。
解雇が無効である場合は、原則として従業員を復職させる必要があります。
従業員と交渉すれば退職を受け入れてもらえるケースもありますが、その場合は多額の解決金を支払う場合が多いです。
また、そもそも不当解雇に関するトラブルに対応すること自体、会社にとっては人件費などの大きなコストを要します。
従業員を解雇する場合は、不当解雇を主張されて大変なことになるリスクに十分注意が必要です。 -
(3)会社の評判が低下するおそれがある
内部リークなどによって、「従業員を簡単に解雇する会社だ」というようなイメージが広まると、会社の評判は低下してしまいます。
その結果、新規人材の採用が難航するなどの弊害が生じるおそれがある点に要注意です。 -
(4)助成金等の受給が制限されることがある
国が設けている助成金の中には、雇用関係助成金などをはじめとして、「生産性要件」が設けられているものがあります。
生産性要件を満たすと助成金が割り増しされます。しかし、一定期間内に従業員を会社都合退職させた(解雇・退職勧奨)事業者は、生産性要件を満たすことができません。
従業員を解雇すると、受給できる助成金の額が減ってしまうことがある点にご注意ください。
参考:「労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます」(厚生労働省)
3、解雇が有効と判断されるためのポイント
適法・有効に解雇を行うためには、各解雇の要件について十分な検討を行う必要があります。普通解雇・整理解雇・懲戒解雇のそれぞれについて、解雇が有効と判断されるために留意すべきポイントを解説します。
-
(1)普通解雇の場合|改善・解消の可能性を検討する
普通解雇を行う際には、労働契約や就業規則における解雇事由に当たるかなどの解雇理由として合理的かどうかに加えて、解雇事由について改善・解消の可能性があるかなど労働者の雇用喪失という不利益に相応する事情の有無についても検討すべきです。
たとえば、私傷病により長期間にわたって休業している従業員については、解雇事由に該当するケースが多いです。
しかし、従業員が間もなく復帰できそうな場合には、普通解雇によって復帰の道を閉ざしてしまうのは不適切であり、解雇が無効と判断される可能性が高いと考えられます。
解雇権濫用の法理に抵触しないように、解雇事由を改善・解消できる余地がないと判断した場合に、はじめて普通解雇を決断しましょう。 -
(2)整理解雇の場合|代替手段を十分講じる・対象者を公正に選ぶ・説明を尽くす
整理解雇を行う際には、それに先立って役員報酬の削減・希望退職者の募集・新規採用の抑制などの代替手段を十分に講じなければなりません。
やむを得ず整理解雇をする場合は、合理的な基準を策定した上で、その基準を適切に運用して対象者を選定する必要があります。人事権者の好き嫌いで整理解雇の対象者を選ぶようなことがあってはなりません。
整理解雇の実施が決まったら、対象者や労働組合に対して十分に説明を尽くし、納得を得るよう努めましょう。 -
(3)懲戒解雇の場合|悪質な行為に限る・段階的に懲戒処分を行う
懲戒処分の内容は、労働者の行為の性質・態様等に釣り合ったものとしなければなりません。
懲戒解雇は最も重い懲戒処分なので、犯罪に当たる行為や会社に対する重大な背信行為など、悪質な行為に対象を限定すべきです。
また、犯罪などのきわめて悪質な行為を除き、懲戒解雇を行う前に、軽い懲戒処分から段階的に行うことをおすすめします。
戒告・減給・出勤停止・降格などの懲戒処分を行い、改善が見られなければ段階的に処分を引き上げる形をとれば、最終的に懲戒解雇をすることになっても、無効と判断されるリスクが低くなります。
4、会社が従業員を解雇する際の注意点
会社が従業員を解雇するに当たっては、解雇の要件を満たしていることを立証できるようにしておく必要があります。そのためには、解雇理由に関する証拠を十分に確保すべきです。弁護士のアドバイスを踏まえて、不当解雇を主張されても戦えるだけの証拠を確保しましょう。
また、従業員を解雇することには大きなリスクが伴うので、できる限り解雇は避けた方が無難です。解雇を避けつつ従業員を退職させるためには、退職勧奨を行うことが考えられます。退職勧奨を従業員が受け入れれば、合意退職の形をとることで解雇トラブルのリスクを回避できます。
ただし、退職勧奨は従業員の自由な意思決定を尊重することが必要なので、退職勧奨による退職を実現する場合には、退職金の上積みなどのメリットを提示しなければならないケースが多いです。
会社としてどの程度のコストを負担できるか、および解雇のリスクを総合的に考慮した上で、退職勧奨と解雇のどちらを選択するか適切に判断しましょう。
お問い合わせください。
5、まとめ
従業員を解雇することには、会社にとって多くのデメリット・リスクが伴います。退職勧奨などの代替手段も視野に入れつつ、弁護士のアドバイスを受けながら、本当に従業員を解雇してもよいかどうか適切に判断しましょう。
ベリーベスト法律事務所 越谷オフィスでは、従業員の解雇などに関する企業のご相談を随時受け付けております。従業員を解雇すべきかどうか迷っている企業や、解雇手続きを適切な形で進めたい企業は、まずは当事務所までご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています