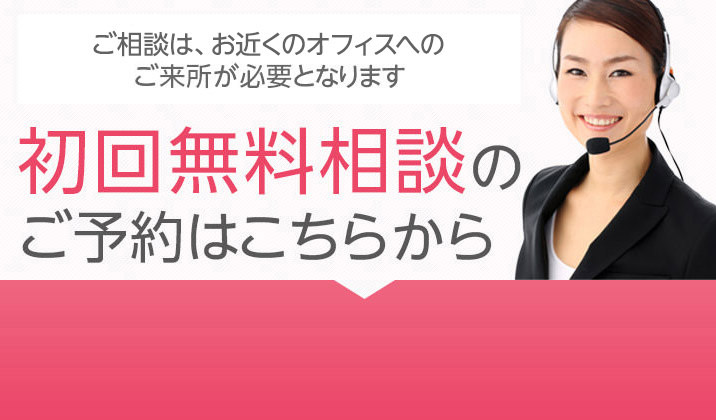子どもへの虐待を理由に離婚できる? 注意点や離婚の進め方を解説
- 離婚
- 離婚
- 虐待

埼玉県が公表している統計によると、令和4年度に埼玉県内の児童相談所における児童虐待相談対応件数は、1万8877件で、前年度よりも1271件の増加となっています。
子どもへの虐待は、暴力による「身体的虐待」だけでなく、子どもの目前でする夫婦喧嘩やDVなども「心理的虐待」にあたります。このような虐待を理由に夫婦が離婚をすることができるのでしょうか。
今回は、子どもへの虐待を理由に離婚できるかどうか、虐待を理由に離婚をする際の注意点と進め方などをベリーベスト法律事務所 越谷オフィスの弁護士が解説します。


1、子どもへの虐待を理由に離婚できる? 虐待としつけの違いとは
子どもへの虐待を理由に離婚することはできるのでしょうか。また、しつけと虐待とはどのような違いがあるのでしょうか。以下で詳しくみていきましょう。
-
(1)子どもへの虐待は離婚理由になり得る
離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあり、互いに合意さえすれば協議離婚や調停離婚で離婚が可能です。
もし話し合いで相手が離婚を拒否した場合、裁判離婚となりますが、以下のような法定離婚事由がなければ裁判による離婚はできません。- ① 不貞行為
- ② 悪意の遺棄
- ③ 3年以上の生死不明
- ④ 回復の見込みのない強度の精神病
- ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由
子どもを虐待する配偶者と婚姻生活を継続していくのは困難ですので、子どもへの虐待が明らかであれば「⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚できる可能性があります。
裁判離婚には物的証拠を集めることが重要となります。証拠については「4、(1)児童虐待の証拠を確保する」で後述します。 -
(2)児童虐待としつけとの違い
しつけとは、子どもがどのように行動すればよいかを導くことをいいます。しつけを理由に子どもへの体罰を正当化する親もいますが、体罰は基本的には許されない行為です。
これに対して、子どもをたたく、殴る、食事を与えない、子どもの存在を軽んじるような言動は、児童虐待にあたり、状況によっては犯罪となる可能性もあります。
なお、以前は民法において「懲戒権」が定められていましたが、令和4年12月16日施行の改正民法により懲戒権の規定は削除されました。それに伴い、体罰など子どもの心身の健全な発達に悪影響をおよぼす言動が、明確に禁止されるようになりました。
2、子どもに対する虐待の種類と特徴
子どもに対する虐待には、以下のような種類と特徴があります。
-
(1)身体的虐待
身体的虐待とは、子どもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えることをいいます。
具体的には、以下のような行為が身体的虐待にあたります。- 殴る、蹴る
- 首を絞める
- 投げ落とす
- 熱湯をかける
- 逆さつりにする
- 異物を飲み込ませる
- 真冬に戸外に放置する
状況によっては暴行罪や傷害罪に該当する可能性もあります。警察へ相談した事実は裁判離婚や慰謝料の証拠にもなり得ますので、危険を感じた場合は最寄りの警察署へ相談することをおすすめします。
-
(2)性的虐待
性的虐待とは、子どもに対しわいせつな行為をする、またはさせることをいいます。わいせつ行為は、直接的に性行為をすることだけでなく、裸の写真を撮影することや誰かと性行為をするのを強要することも含まれます。
具体的には、以下のような行為が性的虐待にあたります。- 子どもと性行為をする
- 子どもに自分の性器を触らせる
- 子どもの性器を触る
- 子どもを裸にして撮影する
- 子どもに第三者と性行為をさせて金品を得る
-
(3)ネグレクト(育児放棄)
ネグレクトとは、子どもの心身の正常な発達を妨げるような放任や不適切な育児をいいます。ネグレクトのことを「育児放棄」と表現することもあります。
具体的には、以下のような行為がネグレクトにあたります。- 子どもに食事を与えない
- 子どもを長時間ひとりにしたまま放置する
- 同居人による子どもへの虐待を知っていながら放置する
- 子どもが病気になっても病院に連れていかない
-
(4)心理的虐待
心理的虐待とは、子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うことをいいます。心理的外傷とは、子どもの心を死なせてしまうよう言動や体験のことをいい、身体的虐待のようなわかりやすい傷跡が残らないのが特徴です。
具体的には、以下のような行為が心理的虐待にあたります。- 子どもの前で夫婦喧嘩やDVをする
- 兄弟間で差別的な扱いをする
- 子どもの存在を否定するような言葉を投げかける
- 無視や拒否的な態度をとる
- 大声で怒鳴るなどして恐怖に陥れる
3、子どもを虐待する配偶者との離婚を考えるときの注意点
子どもを虐待する配偶者との離婚をお考えの方は、以下の点に注意が必要です。
-
(1)子どもの安全を確保するために別居を検討する
子どもに虐待をする配偶者と同居したまま離婚の話し合いを進めると、逆上した配偶者により子どもへの虐待がエスカレートする危険があります。
そのようなリスクがあるときは子どもの安全を守るためにも、相手と別居をしてから離婚の話し合いを進めた方がよいでしょう。 -
(2)心身に重大な危害を受けるおそれがあるときは保護命令の申立てをする
配偶者が子どもだけでなくあなたにも虐待をするようであれば、保護命令の申立てを検討するとよいでしょう。
保護命令とは、DV防止法(配偶者暴力防止法)に基づき、配偶者からの身体的暴力を防ぐために裁判所が以下のような決定をすることができる制度です。- 接近禁止命令
- 電話等禁止命令
- 子への接近禁止命令
- 親族等への接近禁止命令
- 退去命令
申立手数料は1000円(+切手代)で、通常は申立てから7日以内に決定が下されます。緊急性が高いケースでは、さらに迅速な処理になる可能性もあります。
暴力の加害者が保護命令に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。 -
(3)虐待をしていた配偶者に対しては慰謝料請求が可能
子どもへの虐待が原因で婚姻関係が破綻したといえる場合には、子どもを虐待していた配偶者に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
配偶者への暴力も含まれている場合には、慰謝料の増額事由になりますので、相場よりも高額な慰謝料を請求することが可能です。 -
(4)子どもとの面会交流は慎重に判断する
裁判所は、離婚後も親と子どもが継続的に交流することが望ましいと考えていますので、特別な事情がない限りは、面会交流を実施する方向で調整してきます。
しかし、子どもへの虐待がある事案では、面会交流を実施することで子どもに危害がおよぶおそれがありますので、面会交流の実施は慎重に考えていかなければなりません。虐待のおそれがあるという場合には、面会交流を実施しないという結論も尊重されるでしょう。 -
(5)養育費の不払いに備えた対策が必要
離婚時に養育費の取り決めをしたとしても、子どもへの虐待をするような親だと養育費の支払いを滞る可能性があります。
協議離婚をする場合には、すぐに強制執行をして滞納分の養育費を回収できるようにするためにも、公正証書の形式で離婚協議書を作成するのがおすすめです。 -
(6)相手との交渉は弁護士に任せるのが安心
子どもへの虐待をするような相手に対して離婚を切り出すと、逆上してあなたに対しても暴力を振るう可能性があります。当事者同士で交渉をするのはリスクが高いため、相手との交渉は弁護士に任せるのが安心です。
弁護士であれば、あなたに代わって相手との交渉を行うことができますので、あなたや子どもへの虐待のリスクを回避することができます。ご自身で対応するのが不安だという場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。
お問い合わせください。
4、子あり家庭における有利な離婚の進め方
子どもへの虐待を理由に離婚をする際には、以下のように進めていくのがおすすめです。
-
(1)児童虐待の証拠を確保する
子どもへの虐待を理由に離婚をするのであれば、虐待の証拠を確保することが重要です。
子どもへの虐待が立証できれば、子どもの親権を獲得できる可能性が高くなりますし、慰謝料を請求することも可能になります。また、子どもへの虐待は、法定離婚事由に該当しますので、相手が離婚を拒否していたとしても離婚することが可能になります。
児童虐待の証拠としては、以下のようなものが挙げられます。- 子どもの虐待をしている状況の録画や録音
- 子どもが怪我をしたことがわかる診断書
- 子どもが怪我をした部位を撮影した写真
- 子どもへの虐待に関する内容が含まれているメールやLINE
- 子どもへの虐待を児童相談所などの公的機関に相談した記録
- 子どもへの虐待があったことを記載した日記
-
(2)適切な法的アドバイスを受けるために弁護士に相談する
子どもに対する虐待により婚姻関係が破綻したといえる場合には、それに基づいて有利に離婚手続きを進められる可能性があります。
離婚にあたっては、親権、養育費、慰謝料、財産分与、面会交流など決めなければならない事項が多岐にわたります。離婚問題の解決実績がある弁護士のサポートを受けながら、適切な条件で離婚することを目指しましょう。
ベリーベスト法律事務所には離婚問題の解決実績がある弁護士が所属しています。身の安全を確保しながら有利に離婚手続きを進めるためにも、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。
お問い合わせください。
5、まとめ
子どもへの虐待がある場合には、それを理由に離婚や慰謝料請求が可能です。ただし、「虐待」には、さまざまな種類があり、虐待ごとに集めるべき証拠が異なってきます。
安全かつスピーディーに離婚を進めるためには、離婚問題の解決実績がある弁護士のサポートがとても重要です。ベリーベスト法律事務所 越谷オフィスの弁護士は、これまでの解決実績と知見に基づき、あなたのお悩みに親身に寄り添います。
虐待により相手との離婚を考えている場合は、ひとりで悩まず早めにベリーベスト法律事務所 越谷オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています