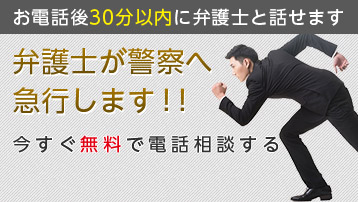勾留に対する準抗告とは? 身体拘束への対処法を解説
- その他
- 準抗告
- 勾留

越谷市統計年報によると、令和4年に埼玉県越谷市内で発生した刑法犯罪は2445件でした。
逮捕された被疑者は最長72時間身柄を拘束されますが、勾留に移行するとさらに最長20日間拘束されてしまいます。「準抗告」は、起訴前の勾留処分などに対して異議を申し立てる手続きです。できる限り早期の身柄解放を目指すためには、準抗告などを弁護士に依頼しましょう。
本記事では、勾留に対する準抗告などについてベリーベスト法律事務所 越谷オフィスの弁護士が解説します。


1、準抗告とは?
「準抗告」とは、裁判官や捜査機関が行った処分に対して、被疑者または被告人が不服を申し立てる手続きです(刑事訴訟法第429条、第430条)。
-
(1)刑事手続きの大まかな流れ
刑事手続きは、大まかに以下の流れで進行します。
① 捜査段階(起訴前) - 逮捕
- (起訴前)勾留
- 証拠物等の捜索、差押え
② 検察官による処分 - 起訴もしくは不起訴の決定
③ 公判段階(起訴後) - (起訴後)勾留
- 保釈
- 公判手続き(刑事裁判)
- 判決、刑の執行
準抗告は、主に起訴前の段階で行われる裁判官や捜査機関の処分に対して行うこともできます。
また、起訴後の段階においても、第一回公判期日までに裁判官が行う処分の一部が準抗告の対象とされています。 -
(2)準抗告と他の種類の抗告の違い
刑事訴訟法では、不服申立ての手続きとして以下の種類の「抗告」が認められています。
・抗告(刑事訴訟法第419条)
裁判所のした決定に対する不服申立てです。特に期限は設けられていません。
・即時抗告(同法第420条)
裁判所の管轄または訴訟手続に関して、裁判所がした決定に対する不服申立てです。
即時抗告の期間は3日間に限定されています。
・準抗告(同法第429条、第430条)
裁判官、検察官または検察事務官が行った処分に対する不服申立てです。
・特別抗告(同法第433条)
通常は不服を申し立てることができない決定または命令に対し、上告事由があることを理由として、最高裁判所に不服を申し立てる手続きです。
特別抗告の期間は5日間に限定されています。
通常の抗告は裁判所の決定に関する不服申立てであるのに対し、準抗告は裁判官、検察官または検察事務官の処分に対する不服申立てです。
裁判所が決定を行うのは公判手続きの開始以降なので、通常の抗告を行うのもそれ以降となります。これに対して、第1回公判期日前の処分については、その一部が準抗告の対象とされています。
2、準抗告の対象となる裁判・処分
準抗告の対象となるのは、以下に挙げる裁判・処分です。
-
(1)忌避の申立てを却下する裁判
公平な裁判が期待できない裁判官について、検察官・被告人・弁護人は忌避を申し立てることができます(刑事訴訟法第21条)。忌避された裁判官は、刑事手続きから除外されます。
忌避の申立てを却下する裁判に対しては、準抗告が認められています(同法第429条第1項第1号)。 -
(2)勾留・保釈・押収・押収物の還付に関する裁判
起訴前、および起訴後第1回公判期日までは、被疑者・被告人の勾留処分(勾留延長を含む)は裁判官が行います(刑事訴訟法第207条、第280条第1項)。
裁判官による勾留処分に対しては、準抗告が認められています(同法第429条第1項第2号)。
これに対して、第1回公判期日後の勾留処分は裁判所が行うため、不服申立ての手続きは通常の「抗告」となります。
勾留のほか、保釈・押収・押収物の還付に関する裁判も、裁判官が行うものについては準抗告の対象とされています。 -
(3)鑑定のため留置を命ずる裁判
刑事事件の被疑者・被告人の責任能力の有無を確認する目的で、鑑定のために身柄を留置する処分が行われることがあります。
鑑定のための留置を命ずる裁判は、第1回公判期日前は裁判官が行います(刑事訴訟法第179条第1項、第2項)。裁判官が行う鑑定のための留置を命ずる裁判は、準抗告の対象です(同法第429条第1項第3号)。 -
(4)証人等に対して過料または費用の賠償を命ずる裁判
召還を受けた証人・鑑定人・通訳人・翻訳人が、正当な理由なく出頭しない場合や宣誓を拒んだ場合は、決定によって過料に処され、かつ拒絶のために生じた費用の賠償を命じられることがあります(刑事訴訟法第150条第1項、第160条第1項、第171条、第178条)。
証人等に対して過料または費用の賠償を命ずる裁判は、第1回公判期日前は裁判官が行い、準抗告の対象となります(同法第429条第1項第4号)。 -
(5)身体の検査を受ける者に対して過料または費用の賠償を命ずる裁判
刑事手続きに関しては、被疑者・被告人やその他の者に対して身体検査が命じられることがあります。
正当な理由なく身体検査を拒んだ場合は過料に処されるほか、拒絶によって生じた費用の賠償が命じられます(刑事訴訟法第133条第1項、第137条第1項)。
身体の検査を受ける者に対して過料または費用の賠償を命ずる裁判は、第1回公判期日前は裁判官が行い、準抗告の対象となります(同法第429条第1項第5号)。 -
(6)接見等の日時・場所・時間を指定する検察官等の処分
検察官、検察事務官、司法警察職員は、捜査に必要があるときは、公訴の提起前に限り、被疑者との接見または書類や物の授受に関し、その日時・場所・時間を指定することができます。ただしその指定は、被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはなりません(刑事訴訟法第39条第3項)。
接見または書類や物の授受の日時・場所・時間を指定する検察官等の処分は、準抗告の対象とされています(同法第430条第1項、第2項)。 -
(7)押収・押収物の還付に関する検察官等の処分
検察官、検察事務官または司法警察職員は、捜査のため必要があるときは、令状に基づき、または逮捕の現場において物を差し押さえることができます(刑事訴訟法第218条第1項、第220条第1項)。
ただし、緊急逮捕の現場において物を差し押さえた後に逮捕状が得られなかったときは、差押物を直ちに還付しなければなりません(同法第220条第2項)。
押収・押収物の還付に関する検察官等の処分は、準抗告の対象とされています(同法第430条第1項、第2項)。
3、勾留に対する準抗告を成功させるためのポイント
勾留処分に対する準抗告が認められるためには、勾留の法的根拠を崩すことが大切です。具体的には、勾留の「理由」及び「必要性」がないことを主張します。
- 住居不定
- 罪証隠滅のおそれ
- 逃亡のおそれ
② 勾留の必要性
身柄拘束の必要性(犯罪の重さや罪証隠滅・逃亡のおそれなど)が、被疑者(被告人)の被る不利益を上回ること
弁護人のサポートを受けながら、準抗告に当たってどのような主張を行うかを検討しましょう。
4、勾留から解放されるための対処法
勾留による身柄拘束は、起訴前・起訴後を合わせると相当長期間に及ぶことがあります。1日も早い身柄解放を目指すためには、弁護人と協力して以下の対応を行いましょう。
-
(1)勾留理由の開示請求
勾留されている被疑者や被告人は、それぞれ勾留の理由の開示を請求することができます(刑事訴訟法第82条、第207条)。弁護人などによる開示請求も可能です。
勾留処分に対して不服を申し立てる際の論拠を検討するため、まずは勾留理由の開示請求を行いましょう。 -
(2)勾留決定に対する準抗告・抗告
裁判官による勾留処分に対しては準抗告、裁判所による勾留処分に対しては抗告ができます。
勾留の理由及び必要性を崩すことができれば、準抗告や抗告が認められて身柄が解放される可能性があります。 -
(3)勾留の取り消し請求
勾留決定後の事情により、勾留の理由及び勾留の必要がなくなったときは、勾留されている被疑者(被告人)やその弁護人などは、裁判官(裁判所)に対して勾留の取消しを請求できます(刑事訴訟法第88条、第207条)。
また、勾留による拘禁が不当に長くなった場合も、勾留の取り消し請求が認められています(同法第91条)。 -
(4)勾留の執行停止の申立て
裁判官(裁判所)は、適当と認めるときは、勾留されている被疑者(被告人)を親族・保護団体その他の者に委託し、または住居を制限して、勾留の執行を停止することができます(刑事訴訟法第95条、第207条)。
たとえば以下のようなケースでは、勾留の執行停止が認められる可能性があります。- 病気やけがの治療を受ける必要がある
- 家族の冠婚葬祭に出席する
- 入学試験や卒業試験を受ける
-
(5)保釈請求(起訴後のみ)
起訴された被告人は、裁判所に対して保釈を請求することができます。保釈請求が認められれば、保釈保証金を預けることを条件として、一時的に身柄が解放されます。
保釈請求は、犯罪の種類や前科の状況、罪証隠滅のおそれなどの事情によって判断されます(刑事訴訟法第89条、第90条)。 -
(6)不起訴に向けた弁護活動
不起訴処分となれば、身柄拘束から解放され、刑罰を受けることもなくなります。
罪を犯したことが事実であっても、情状によっては起訴猶予(不起訴)となることがあります。被害者との示談や反省文の作成など、罪を償おうとする行動をして、弁護人を通じて検察官に示しましょう。
お問い合わせください。
5、まとめ
犯罪捜査の対象になってしまったら、速やかに弁護士へ相談しましょう。準抗告をはじめとする様々なアプローチにより、早期の身柄解放を目指したサポートを受けられます。
ベリーベスト法律事務所は、刑事事件に関するご相談を随時受け付けております。自分や家族が逮捕されるのではないかと心配な方は、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています